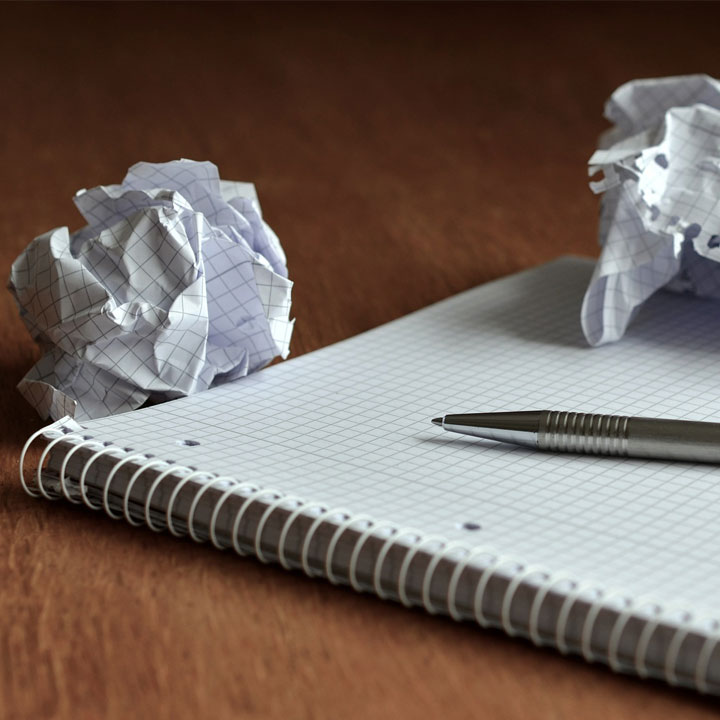転職が決まらない人の特徴
転職が思うように決まらない人にはいくつかの特徴があると言われていますが、「志望動機の弱さ」や「履歴書の使い回し」、「読みづらい職務経歴書」など、どの特徴も自分次第で修正できるものばかりです。直すべきことを直さないままにしておくと、いくら転職活動を頑張っても良い結果にはなりません。自分自身を見つめ直すためにも、それらの特徴がどのようなものかを知り、当てはまる点を改善してからもう一度転職にチャレンジしてみましょう。
-
志望動機が弱い
思うように転職が決まらない人に多い特徴のひとつに「志望動機の弱さ」があります。志望動機は企業にとって重要なポイントなので、この部分が弱い人は最初にはじかれてしまうでしょう。志望動機の詰め方がもともと甘い人は、何社応募しても選考を通過できないという負のスパイラルに陥ってしまうことがあるので、落ちてはまた次をすぐ受けるのではなく、志望動機に改善点がないか自己分析してみることを優先した方がいいかもしれません。
-
履歴書の使い回し
転職活動が長引いてくると、手間を省くために履歴書の使い回しをする人もいますが、それが原因で転職が決まらないという状況に陥っている可能性もあります。履歴書の中で自分の意思を反映させられるのは志望動機や自己PR欄ですが、同じ業界、職種に応募し続けていると、どこにでも通用する無難な内容にしてしたくなるかもしれません。しかし、それを続けている限り、「この企業で働きたい」という熱意を伝えることはできないでしょう。
-
職務経歴書がわかりにくい
職務経歴書がわかりにくいものだと、書類選考で落ちてしまう確率がかなり高くなります。実際、転職が決まらない人は、職務経歴書に問題があるケースが多く、改善しないままだとさらに転職活動を長引かせてしまうことになりかねません。職務経歴書のフォームは基本的に自由ですが、内容や書き方について好ましくないことははっきりしているので、転職が思うようにいかないなら、自分の職務経歴書を見直してみる必要があるかもしれません。
-
あらゆる準備が不足している
転職がなかなか決まらない人は、事前準備を怠っているケースが多いです。企業リサーチや自己分析が甘いと、面接担当者に魅力的な人材だと判断してもらえない可能性が高くなります。面接対策を怠った場合、社会性が低い人物だとマイナスの印象を持たれてしまうこともあります。企業が求める人物像や自分自身のことを深堀りし、万全の体制で面接に挑みましょう。
ニュース
-
明確な基準
うまく転職できる人は、退職理由や志望動機が明確です。そのように転職に関する自分の考えを明確にするためには自己分析がまず欠かせません。退職や将来のことを漠然とイメージするのではなく、退職であれば、何が不満で何をしたかったのか、将来はどのようなキャリアを目指し、そのために何をすべきかなどひとつひとつを丁寧に考えていく必要があります。そうすることで、自分の希望に合う最適の企業探しを行うことができるようになるのです。
-
エージェントの効果的な活用方法
転職活動をする際に心強い味方となってくれるのが、「転職エージェント」です。今では多くのエンジニアが活用していますが、使い方次第ではもったいない利用の仕方をしているかもしれません。できれば転職エージェントは1社だけでなく、複数登録する方が選べる求人が増え、多くの選択肢の中から理想に近い求人を探せるでしょう。また、担当者へは自分のアピール材料となる情報に加え、希望する収入額などを正直に伝えることも大切です。
-
あらゆる準備が不足している
転職活動で成功するためには、まず応募する企業についてしっかりと調べることが大切です。企業の求めるスキルや理念を理解していないと、良い印象を与えられません。また、自分自身をしっかりと分析し、自分がどのような強みを持っているのかを明確にしましょう。学生時代の経験などを掘り下げることで、面接での説得力が増します。さらに、面接対策も十分に行い、清潔感ある身だしなみとハキハキとした受け答えを心がけることが大切です。
おすすめの記事
-
業務に役立つ資格
資格は持っていた方が転職には有利ですが、資格ならどのようなものでもいいというわけではありませんし、資格を取ることばかりに時間をかけてしまうと、肝心の転職活動が進まなくなってしまいます。そこで、幅広い分野に応用できる資格で代表的なものをいくつかご紹介します。全ての資格を持つ必要はありませんが、どれか1つでもあると転職活動をより有利に進めることができるかもしれないので、自分にできそうなものから挑戦してみてはいかがでしょうか。
-
企業と求職者のマッチング
転職エージェントには、数多くの求人情報が寄せられていますが、一般の求人サイトとは違って会員しか知ることのできない非公開求人の情報も豊富です。求職者は、エージェントから求人を紹介してもらえるだけでなく、応募先の特徴に合わせた履歴書や職務経歴書の書き方、面接対応の方法なども教えてもらえます。不安なことやわからないことはなんでも相談できるので、転職が決まらない状況を繰り返して1人で落ち込むことはもうありません。
-
最終面接で問われるビジョン
採用までの過程においては、何度か面接を通過しなければなりませんが、最終面接は予測不可能な質問が飛んでくる可能性があります。最終面接での対応は、社長や役員などの経営トップクラスの人が行うことが多く、型取りのやり方では対応できないこともあります。しかし、経営陣がそこから何を知りたいと思っているかを理解しておけば、予想外の質問があったとしても何を軸に話せばいいかがわかるので、安心して最終面接に臨むことができるようになります。